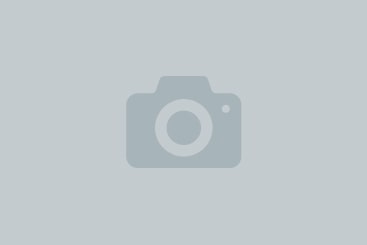【書評】「プロの仕事」とはどうある...
31
01
【書評】「プロの仕事」とはどうあるべきか:ルシアン・ネイハム著『シャドー81』
ここは南ベトナムのダナン空軍基地。おりしも米空軍所属の最新鋭ジェット戦闘爆撃機TX75Eが4機、飛び立とうとしていた。 時は、ベトナム戦争がいよいよ終焉を迎えようとする1970年代半ば――。
戦闘機のパイロット、米空軍大尉のグラント・フィールディングは、コネティカット州スタムフォード出身の30歳。今回の作戦行動では4番機に搭乗している。午前10時とはいえ蒸し暑く、地表にはかげろうが立ち昇り、滑走路の先がぼやけている。基地周辺の環境は劣悪である。 離陸を待つ狭い操縦席の中で、グラントは、「ブロンドの良い男が、こんなはき溜めみたいなところで何をしている?」と毒づいた。
まもなく、隊長機と2番機が出発する。 三番機とグラントも、バレエの群舞のようにぴったり揃って、数秒後には空に舞い上がった。二機はほとんど前には進まないでまっすぐ上に向かってぐんぐん昇り、先の二機に合流して編隊を組んだ。>
このTX75E機は、最新鋭の可変翼型超音速機で、その性能については極秘扱いになっている。物語を読み進むにつれて、次第に明らかになってくるが、翼を折りたたんで狭い空間に格納することができ、飛び立つ際には短い滑走でほぼ垂直に急上昇することができる。長時間の飛行が可能で、航続距離も長い。 実は、この戦闘爆撃機そのものが、物語の影の主役でもある。
行方不明になった最新鋭戦闘機
本作は、1975年に発表され、1977年4月に新潮文庫から邦訳が出版された。のち2008年9月にハヤカワ文庫から新装版が出されたわけだが、世に出てから40年以上経つというのに、いま読んでみてもまったく時代遅れの感じがしない。 古臭さは微塵もなく、いまなお斬新である。 なぜなら、ハイジャックを描いた小説、ドラマ、映画はいくつもある。しかし、犯人が機内に潜伏してというのではなく、旅客機の背後を追走する戦闘機のパイロット、という設定はこの作品以外にありえない。模倣を許さない独創的なアイデアなのである。しかも、抜群に面白い!
では、再びベトナムの戦場に戻る。 北爆のために飛び立った4機は、敵地で猛烈な放火を浴びる。1番機から順に目的とする地点にミサイルを発射、次々と戦線を離脱していくが、その最中、グラント大尉の操縦する4番機が地対空ミサイルに被弾したらしく、編隊から離れていった。
このTX75E機の性能は極秘のため、機体を敵国に渡すわけにはいかない。敵弾で完全に破壊されたならともかく、そうでなければ自爆してパラシュート脱出することが義務づけられている。 しかし4番機は、僚機に状況を説明する暇もなく、交信が途絶えてしまった。撃墜されたのか、それとも自爆して脱出できたのか。目撃した者はいない。
コンテナ型の改造船を発注した男
舞台は香港にうつる。 この地で造船会社を経営するジミー・フォンのもとに謎のアメリカ人が現れる。 自らは作家と名乗り、2隻の中古船舶を購入する。その際に注文があり、1隻は特殊な改造を施して、かなりの荷重に耐えうるコンテナ型の船に仕立てること。さらに、この船を母船として、船中に積み込むことが可能なサイズのモーターボートが必要であるという。 フォンは、薬物かなにかの密貿易に使うのか、あるいはテロリストが武器を運ぶのかと疑ったものの、身許は怪しげだが金払いのよい上得意に船を売りつけることはよくあった。
3週間後、モーターボートを積んだコンテナ船が、密かに香港を離れ、南シナ海の無人島を目指した――。

ここまでが前半のヤマ場。犯人が緻密な計画を立て、ハイジャックにいたるまで用意周到に準備にする様が克明に描かれており、これが迫真のリアリティを生んでいる。読者は、固唾を呑んで、頁をめくることだろう。
犯人は巨額の金塊を要求
「PGA81便、貴旅客機はただいま乗っ取られたことを通告する」ジャンボジェット機の背後にピタリと張り付いた戦闘機のパイロットが、無線で機長に宣言する。 パシフック・グローバル航空81便は、ロサンゼルス空港を飛び立ち、ハワイを目指していた。同機は、高度2万フィートを飛行中にハイジャックされたのだ。乗員乗客あわせ200人あまりが人質となった。 81便の背後に隠れているので、犯人は「シャドー(影)81」を名乗る。 戦闘機は航空機の死角に入っているため姿は見えず、機種は不明だ。
この先、犯人とジャンボ機の機長バートン・ハドレー、そしてロス空港の主任管制官トム・ブレイガンとの間で、緊迫したやり取りが続いていく。 要求は巨額の金塊。地上には、仲間の共犯者がいるという。 どうして金塊でなければならないのか。どこで受け取るつもりなのか。これには深い意味がある。
そして機長に、ある一定の高度で旋回飛行することを指示する。その一方で、管制官へ、すべての航空機がこの空域に、すべての艦船がその下の海域に立ち入らないよう要求する。 ホワイトハウスや軍、FBI、警察など、摘発する側の当局は、人命を最優先し、犯人の指示に従わざるをえない。 ジャンボ機に搭載された燃料からすると、飛行時間は8時間。この刻限の間に、金塊を用意できなければ、燃料切れで航空機は墜落してしまう。また、関係当局がおかしな小細工をすれば、「シャドー81」はたちまちミサイルで同機を撃墜すると宣告する。
ここから先、物語の展開を紹介するのは不可能である。犯人は次々と予想外の指示を出し、当局を翻弄する。犯人はあきらかに上手をいっている。 このあたりは読みごたえじゅうぶん。はたしてハイジャッカーの企ては成功するのか、それとも犯人の逮捕にいたるのか、読者の興味はそこに集約されていく。
「・・・断じて許されません」
だが、この物語が優れている点は、アイデアが斬新なだけではない。 事件を取り巻く群像劇として、それに関わる登場人物たちが巧みに描かれていることである。 その姿は悲劇的であり、また滑稽でもある。それぞれの立場で、人というものは様々な行動をとる。ことに切羽詰まった状況に置かれたときには、露骨に人間性が出る。そのあたりを、著者は見事に書き分けているのだ。だから長く読み継がれている。
さらに、この物語は危機管理という観点からも興味深い。 ことに、感情を抑え冷静に行動する主任管制官と機長の行動には感銘を受ける。乗客をパニックに陥らせない、落ち着いた態度。人命最優先のため、犯人の指示に従い、黙々と適切な措置を講じていく。これぞプロフェッショナルの仕事か。 この、無線を通じた犯人とのやり取りが、本作の読みどころのひとつである。
それとは対照的に、「シャドー81」との交信で手一杯な主任管制官に、直接、余計な口をはさもうとする大統領。これがまた、犯人を刺激して一触即発の危機を招く。 かと思えば、偶然、ハイジャック機に乗り合わせた著名な上院議員が、功名心から犯人との交渉役を買って出て、事態を混乱させる場面がある。 軍は、最新兵器を用いて「シャドー81」を撃墜する計画を立て、大統領に進言する。はたして100%の確率で撃墜できるのか。 そうか、災難は、現場でのやり取りの失敗からではなく、周囲の下手な思惑から降りかかってくるのか、とハラハラさせられる。
主任管制官のブレイガンは大統領に切々と訴える。「閣下、くどいようですが、軍がわたくしの了解を取らないで勝手に動くことのないよう、くれぐれもお願いします。ばらばらに行動することは断じて許されません」 奇妙なことに、犯人のパイロットと機長、主任管制官との間には、交信を通じてプロ同士の信頼感が醸成されもする。
「ひとかどの記者というものは・・・」
文庫の著者紹介によれば、ルシアン・ネイハムは1930年エジプトの生れ。16歳のときからフリーの記者として英仏の新聞に記事を書き、のちにAFPニューヨーク支局で長く活躍したという。自身、パイロットの資格を持っていたからこそ、空を舞台にした迫真の描写が可能となったのであろう。1983年に没。
著者の経歴を読み、本作にはなるほどと思い当たる場面がある。 ロサンゼルス・タイムズのベテラン記者のバーニーが、ハイジャックを嗅ぎ付ける。彼は敏腕記者だが、上司に疎まれ、いまは空港担当に左遷されている。 第一報を打つことができれば、これは大スクープになる。裏を取るために、バーニーは主任管制官と、ある取引をする。この場面が秀逸で痛快! この挿話も、群像劇に厚みを加えているのだが、このバーニーに関する記述が、わたしはたいへん気に入っている。 彼と同じ空港詰めの後輩記者は、有名大学のジャーナリズム学科を卒業したエリート。しかし、バーニーは信用していない。
なぜなら、彼は新聞社の給仕からスタートした(著者同様に)叩き上げで、
マスコミの殺到と混乱が予想される中、主任管制官の部下は、彼をこう評す。「バーニーは老練なプロです。少なくとも、何をやらかすか訳のわからない連中とは違います」
ジャーナリスト出身の著者は、このあたりのエピソードが、是非、書きたかったにちがいない。「ひとかどの記者」、そう呼ばれることは勲章だろう。 そして、この物語には、「ひとかどの男」がなん人も登場する。 面白くないわけがない。
シャドー81
ルシアン・ネイハム(著)、中野圭二(訳) 発行:早川書房 文庫版:501ページ
初版発行日:2008年9月15日 ISBN:978-4-15-041180-0


![【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App 【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_7/2022/3/3/66755df992ff2d2b1e1ab43844ef9f88_0.jpeg)