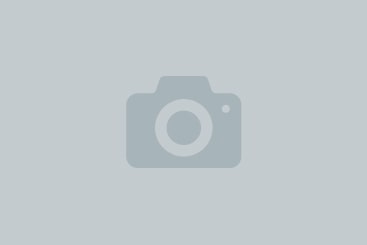ヘリコプターは全自動でも飛ばせるか...
20
10
ヘリコプターは全自動でも飛ばせるか? 難航を極める自律飛行への挑戦
2000年1月11日の朝、アメリカ沿岸警備隊のヘリ操縦士、マーク・ウォードは救難信号を受けて緊急出動した。船がノースカロライナ沖で北東の強風を受けて、沈みそうだというのだ。
ウォードは時速70マイル(時速約112km)の強風に苦労しながらも、なんとか海面から30フィート(約9.1m)の高さでヘリを安定させていた。その間に、ヘリの乗組員が漁船に乗っていた5人全員を無事に引き上げたのだった。
このときの任務は、ウォードが22年間の捜索救難ヘリのパイロットとしての経験のなかで、最も困難なもののひとつだった。そしていま、彼は後輩たちが同じような危険に遭わないための仕事をしている。ヘリコプターメーカーのシコルスキーによる自律飛行ヘリの開発計画で、チーフテストパイロットをしているのだ。
「ある程度の自動操縦が実現するだけでも、ヘリのパイロットの仕事量は減り、ストレスや不安も解消されます」とウォードは言う。「機械には人間が見えないものも見えますし、人間には不可能な情報の処理と対応ができるのです」

いまや、旅客機はほとんどの時間を自動操縦で飛んでおり、ロボットカーが世界中のいろいろな都市でテスト走行をしている。だが、ヘリ自身に飛ぶことを教えるのは、いささか勝手が違う。
ヘリは突風の吹く海上でホヴァリングしなければならないし、強風のなか石油掘削基地に着陸しなければならない。さらには、航空地形図に載っていない送電線や移動通信用鉄塔を身軽にかわし、ケガをした登山者を救助するときはスキッド(ヘリの脚)の片側だけを切り立った崖に降ろさなければならない。
「ヘリコプターは障害物の多い環境下で飛ぶため、パイロットの仕事量は非常に多いのです」と、クリス・ヴァン・ブイテンは言う。彼はロッキード・マーティンの子会社で、自律飛行ヘリを開発しているシコルスキー・イノヴェイションズの副社長だ。
ブイテンによると、ロボットヘリは自律飛行機よりもコンピューターの計算が余計に必要なのだという。特に整備された飛行場を行き来するのではないときにはそうだという。「沈みかかった船が晴れた日にSOSを発することはあまりありません。SOSは雨の降る夜にアラスカ沖で発せられるほうが多いのです」
すでに航空産業は自律飛行ヘリに大金をつぎ込んでいる。2018年5月に、ボーイングの子会社Aurora Flight Sciencesは、開発中の無人貨物輸送システムを「Bell UH-1H 」に搭載し、初めて自動操縦でガソリンと水と医薬品をカリフォルニア州にいた海兵隊員の元に届けることに成功した。
ロッキード・マーティンは07年以来、無人ヘリ「K-MAX」を開発している。遠隔操作や半自動操縦から開発を始めて、11〜14年にはアフガニスタンで物資を輸送した。
AIの役割を最小限に
シコルスキーが開発しているのは、「マトリックス・テクノロジー・システム」と名づけられた自動操縦システムだ。2013年から自社の商業用ヘリ「S-76」にそのシステムを搭載したシコルスキー自動化研究機(Sikorsky Autonomy Research Aircraft=SARA)をウォードが操縦して、実証実験を行っている。その基本的な機能は、アプローチと着陸のために飛行場周辺でトラフィックパターンを飛ぶことと、海上を動く物体に接近し着陸するためにそれを追跡することだ。


![【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App 【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_7/2022/3/3/66755df992ff2d2b1e1ab43844ef9f88_0.jpeg)