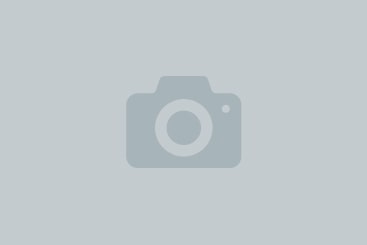Columns talking about Hyperdub UKエ...
27
06
Columns talking about Hyperdub UKエレクトロニック・ミュージックの新局面 | ele-king
2021年のエレクトロニック・ミュージックにおいて、こと複数のメディアで総合的に評価の高かった2枚に、アヤの『im hole』とロレイン・ジェイムスの『Reflection』があり、ほかにもティルザの『Colourgrade』とか、えー、ほかにもスペース・アフリカの『Honest Labour』もいろんなところで評価されていましたよね。まあ、とにかくいろいろあるなかで、やはりアヤとロレイン・ジェイムスのアルバムは突出していたと思います。この2枚は、ベース・ミュージックの新たな展開において、10年代のアルカそしてソフィーといった先駆者の流れを引き寄せながら発展させたものとしての関心を高めているし、そしてまた、〈ハイパーダブ〉という21世紀のUKエレクトロニック・ミュージックにおける最重要レーベルの新顔としての注目度の高さもあります。ロンドン在住の現役クラバー、高橋勇人と東京在住の元クラバー、野田努がzoomを介して喋りました。
■アヤとは何者?
Aya im holeHyperdub/ビート高橋:先週はコード9に会いましたよ。
野田:なんで?
高橋:イースト・ロンドンのダルストンにある〈Café Oto〉というヴェニュー。大友(良英)さんや灰野(敬二)さんがよくやってる。
野田:うん、わかる、日本でも有名。Phewさんの作品も出してるよね。
高橋:そこでアヤがインガ・コープランドの新名義ロリーナと対バンしたんですよ。
野田:くっそー、その組み合わせ、最高だな。
高橋:インガ・コープランド、とくにハイプ・ウィリアムスって、ある種、ダンス・ミュージック以外にも注目しはじめた第二期〈ハイパーダブ〉を象徴するアーティストですよね。
野田:そう、いまハイプ・ウィリアムスの話からはじめようと思ってた。高橋くんって、(マーク・)ロスコの原画って見たことある?
高橋:テート(・モダン)で見たことあります。
野田:あの抽象表現絵画って絵葉書とかになってたりするけど、原画はものすごく巨大で。
高橋:ウォール・ペインティングですもんね。
野田:あの原画の前に立ち尽くすと、圧倒的なものを感じるんだよね。俺はドイツの、たしかデュッセルドルフで原画を見たんだけど、しばらくその前から動けなかったぐらい圧倒された。ハイプ・ウィリアムスのライヴは、自分が21世紀で観てきたなかでいまだベストなんだけど、そのときのハイプ・ウィリアムスのライヴは、言うなればジャングルやベース・ミュージックの抽象絵画だったんだよ。
高橋:なるほど。
野田:抽象化されたベース・ミュージック。そのときのライヴは、壮絶な電子ドローンからはじまったの。サブベースありきのね。もし、“ドローン・ダブ” なんて言葉があるとしたら、あれこそまさにそんな感じだった。それで最初にアヤを聴いたとき、ハイプ・ウィリアムスの続きがここにあると思ったんだよ。ほら、冒頭の電子ドローン、あれを大音量でちゃんとしたシステムで聴いたら、近いモノがあると思うし、電子的に変調された声もそう。
高橋:ははは、そうなんですね。僕にとってハイプ・ウィリアムスとは〈ハイパーダブ〉からの『Black Is Beautiful』ですよ。あのイメージが僕には強い。だから、サンプリングを重視したすごく変なポップ・ミュージックって印象です。
野田:そうだよね。コンセプチュアルでメタなエレクトロニカだよね。とくにその後のディーン・ブラントは音楽そのものを偽装する奇妙でメタなポップ路線に走るけど、あのときのライヴは、言葉が通じない日本人に対してサウンドで勝負したんだよな。そこへいくと、アヤは詩人であり、言葉の人でもある。しかしそのサウンドがあまりにも斬新なんだ。ちなみにさ、アヤってどこから来た人なの?
高橋:経歴を説明すると、出身は北イングランドのヨークシャー。いまって若手のアンダーグラウンドのミュージシャンでも、大学で音楽を勉強している人がすごく多いじゃないですか、ロレイン・ジェイムスとレーベルの〈Timedance〉を主宰しているブリストルのバトゥと彼のレーベルメイトなんかもそうだし。アヤもそうで、音楽大学でミュージック・プロダクションを勉強して、そこで出会ったティム・ランドというランドスライド(Landslide)名義でドラムンベースを作っていた先生に出会うんですよ。その人からアヤはアルカやホーリー・ハードンなどについて学んでいる。
野田:えー、大学でアルカを学ぶって。日本じゃ考えられない(笑)。
高橋:(笑)それがウェールズの大学で、アヤはそこからマンチェスターにいった。そこでベースやUKガラージのシーンへと入って、〈NTS〉マンチェスターとかその周辺の人たちとやっていた。で、『FACT Magazine』のトム・レア元編集長がはじめた、ロンドンの〈Local Action〉レーベルがあって、現行のベース系だけど、ダブステップよりもUKガラージとかから派生している、フロアで機能するようなレーベルです。そういったコミュニティにいたのがアヤ。そこではまだ、ロフト名義でやってた。
野田:ロフト名義のころから注目されてたの?
高橋:詩のパフォーマンスもやってはいたけど、リリースでは音がメインでしたね。ちなみに、トム・レアやその周辺のベース・ミュージックと日本でつながってるのはdouble clapperzのSintaくんとかじゃないかな。
野田:Sinta、素晴らしいな。
高橋:トム・レアってすごく敏腕ディレクターで、新しいことをいろいろやってる。いわゆるEDM的なものではない、カッティング・エッジなベース・ミュージックをロンドンから発信していた。そのなかのひとつとして、ロフトも注目されていた感じです。ロフトはブリストルの〈Wisdom Teeth〉からもリリースしていて、アンダーグラウンドのベース・ミュージック新世代のひとりとして認知されていましたよ。
野田:話が飛んじゃうけど、いまブライアン・イーノの別冊を作っているのね。60年代から70年代って、イギリスはアートスクールがすごかった。アートスクールという教育機関が、70年代のUKロックに影響を与えていたことは事実なんだけど、きっと、いまはそれが大学なんだね。
高橋:まあ、アートスクールが大学ですからね。ブレア政権時代に、いわゆる昔の職業専門学校みたいなのが大学になったりしている。その大学改編の一環で、それまでのアートスクールが大学になっているんじゃないかな。いわゆる美大みたいな感じに。
野田:なるほど。それでアルカについて教えたり、Abletonの使い方を教えたりしてるんだ。そりゃあ面白いエレクトロニック・ミュージックが出てくるわけだな(笑)。ブライアン・イーノがアートスクール時代の恩師からジョン・ケージや『Silence』、VUなんかを教えてもらったようなものだね。
高橋:似ているかもしれない。それこそ僕の在籍しているゴールドスミス大学はジェイムス・ブレイクの出身校ですからね。
Photo by Suleika Müller
野田:話を戻すと、アヤの『im hole』は2021年出たエレクトロニック・ミュージックではいちばん尖った作品だったよね。
高橋:尖ってましたね。
野田:しかもあれって、ベース・ミュージックだけじゃなく、ドローンやアシッド・ハウスとか、いろんなものがどんどん混ざっている。ハイブリットっていうのはまさにUKらしさだし、まあいつものことなんだけど、アヤのそれは抽象化されているんだけど、巧妙で、リズムの躍動感が抜群にかっこいいんだよ。
高橋:僕の好きな曲は4曲目の“dis yacky”です。
野田:あー、わかる、あのベースが唸るやつね(笑)。アルバムを聴いていって、あの曲あたりから踊ってしまうんだよ。部屋のなかで。

高橋:基盤にグライム、ダブステップとジャングルが入ってる。曲の作り方がほかの人とぜんぜん違います。ちなみに、アヤはもともとドラマーでリズム感がめちゃくちゃいいんです。あれって普通に聴くとダブステップと同じようなスピードなんですよ。でも、うしろで鳴ってるのが五連付のドラムロールで、その音だけ、だいたいBPMが170でジャングルと同じなんです。で、アヤはそのBPM170をエイブルトンで設定して作っているんだけど、普通に音楽を聴くときはダブステップやグライムで主流のBPM140で聴こえる。つまりポリリズムですよね。普通はそうやって凝り過ぎるとIDMっぽくなるというか、フロアではシラケちゃったりする。けれどアヤはそこのバランスがうまい、ぜんぜんサウンドオタクっぽく聴こえない。
野田:なるほど、たしかに。
高橋:僕はそこにある種の、ポリリズムとある種のクィアなアイデンティティの相関関係みたいなものがあるんじゃないかと思った。クィア・サウンドとはこれまでにない音を作り出す、それまでのサウンドの境界線をプッシュするというか。そこでポリリズムもリズムの多重性と考えられないかなと。ちなみにアヤ自身はトランスウーマンで、自分のジェンダー自認は女性って公表しているので、その自認がクィア、つまり男性でも女性でもない、というわけではないんですけどね。ただ彼女の生き方には、そういったクィア性はみてとれる。そういった表現をサウンド・テクスチャ―から感じるプロデューサーはいるけど、リズムでやってる人はそこまでいないような気がする。
野田:クィア・サウンド……、なるほどね、それっていま初めて聞いた言葉だけど、面白いね。だって、ハウスはゲイ・カルチャーから来ていて、やっぱりあのサウンドにはその文化固有のエートスが注がれているわけで、最近のエレクトロニック・ダンス・ミュージックでおもろいのは、気がつくとクィアだったりするんだけど、同じようにその独特なノリやその文脈から来ているテクスチュアがあるんだろうね。
高橋:10年代でいえば、〈Night Slugs〉なんかがクィア・シーンではすごい人気ですけどね。
■ソフィーの影響はでかかった
Photo by Suleika Müller
野田:アヤは〈ハイパーダブ〉がフックアップしたの?
高橋:これはスティーヴ・グッドマン(コード9)がロフトのライヴに感銘を受けて、〈ハイパーダブ〉から出したとインスタグラムで言ってました。まずポエトリー・リーディング、詩のパフォーマンスがすごいとも言ってた。そしてあのサウンドテクスチャー。
野田:〈ハイパーダブ〉の資料によると、アヤはクィア文化に対しても批評的なことを言ってるよね。それも俺、興味深く思っててさ、自分がクィアでありながらクィア文化に対しても批評的であるということは、それが「LGBTQであるから評価するのは間違っている」ということだよね?
高橋:そうです。つまり、クィア文化そのものを批判しているんじゃなくて、そこに向けられる言葉に懐疑的なんです。「LGBTのサウンドはこうでしょ、LGBTのアーティストに求められるものはこうでしょ」、といったものを完全に拒否した音楽です。
野田:逆に言うと、それはジェンダーの認識がすごく成熟に向かってるということでもあるのかね。
高橋:そういう見方もできるかもしれません。だからこそかもしれないけど、リリックのなかでクィアなアイデンティティを全面にだすより、単純に自分が感じている日常的なこと、たとえば自分はヨーク出身で、マンチェスターを経由していま音楽をやっているとか、そういうことをうまい言葉遊びで表現してる。だから必ずしも、クィアやLGBTを取り巻く言説に対する批判だけにとどまらないアティチュードが面白いんですよ。
野田:言い方を変えれば、ジェンダーを超えたところで評価してほしいってことだよね。
高橋:もちろん。アヤはソフィーからの影響が強いアーティストなので。
野田:あらためて思うけど、ソフィーはホント、でかいなぁ。
高橋:ソフィーなんてでてきた当初、誰がやっているかさえわからなかったじゃないですか。でも、ブリアルとぜんぜん違うのはメディアとかにもでていて、ソフィーが顔をだすまえ、つまりアルバム『Oil Of Every Pearl's Un-Insides』を出す前、インタヴューを受けても顔を隠して声も変えたりしてた。
野田:まさにそれはアヤもやってることだよね。
高橋:そう。〈NTS〉のラジオでもずっとやってた。ソフィーの影響だと思う。このアルバムにはソフィーが死んだ数日後に作ったという“the only solution i have found is to simply jump higher”という曲が入ってます。僕が買った『im hole』の本の謝辞にも「ソフィへ、すべての永遠の満月を(To SOPHIE for every full moon forever)」って書いてある。ポスト・ソフィーっていい区切りになりますよ。サウンド・ミュータントを追求するアルカやフロアで革新性を求めた〈Night Slugs〉もすごく影響力があるけど、ソフィーがやったハイパーポップがもっと重要みたいです。アヤとロレイン・ジェイムスはふたりともソフィーの影響下にありますからね。
野田:ああそうだね、ロレインも。
Photo by Suleika Müller
高橋:去年、僕が感動したDJは、ロレイン・ジェイムスが〈NTS〉でやったソフィーへのトリビュート・セット。あれは素晴らしい。ソフィーの楽曲だけじゃなくて、そのカバーもミックスしていて、みんなのソフィー像が浮かび上がってくるみたいなんです。 LGBTコミュニティに属するアーティストの紹介と言う意味でも、〈ハイパーダブ〉も頑張っていますね。クィア・アーティストとか、マージナルなアイデンティティの人をよくだすようになった。サウス・アフリカのエンジェル・ホ(Angel-Ho)とか。
野田:ところでアヤのライヴってどうだった?
高橋:2回観てますけど、去年のライヴ・ハウスみたいなとこでやったのは、黒いパーカーを着てステージにあらわれて、体を使ったボディ・パフォーマンスがすごかった。本人はスケボーもやっていて運動神経がすごくいいんです。
野田:あれで運動神経がいいなんて、ちょっと反則だ(笑)。
高橋:なんて言えばいいのかな……、ソフィーやアルカも、ライヴをやってるときってけっこうシリアスな感じになるんですね。でもアヤはそういう感じではない。どんなにシリアスになったときでも、アヤはお客さんとジョークを交えたコミュニケーションを取ることを忘れない。
野田:北部の人たちは、昔からロンドンのお高くとまったところに対抗意識を持ってるんだよ。
高橋:ありますね(笑)。うまく言えないんだけど、すごくイギリス人っぽいユーモアを持ったひとです。だからアルバムからは想像できないけど、すごくフレンドリーです。じょじょに曲が進むとパーカーを脱いで、すごくかっこいい衣装になってダンスしまくる、みたいな。その日はちょうど、アルバムにも参加してるマンチェスターのアイスボーイ・ヴァイオレットもMCでステージに現れました。アイスボーイのジェンダープロナウンは「They/Them」で、男性と女性でもないことを自認していますね。
野田:はぁ……(深くため息)、いまコロナじゃなきゃ、日本でもきっと見れたんだろうなぁ。君がうらやましいよ。じゃ、ロレイン・ジェイムスのことを話そう。彼女は〈ハイパーダブ〉が見つけたんじゃなく、ロレインが海賊ラジオに出演したとき、これは〈ハイパーダブ〉が契約しなきゃだめだろってリスナーが騒いで、で、〈ハイパーダブ〉が契約したっていう話を読んだんだけど。
高橋:たしかに。ロレインは同じ世代からの信頼がすごく厚いプロデューサーなんです。オブジェクト・ブルーというロンドンのプロデューサーや、ロレイン・ジェイムスのフラット・メイトで、〈Nervous Horizon〉を運営するTSVIと彼女は仲がいい。みんな非常にスキルフルで影響力のある作り手たちです。そういったロンドンのコミュニティがあるのは面白いですよね。
野田:面白い話だね。そういうのは日本からはぜんぜんわからないよね。
高橋:オブジェクト・ブルーさんは日本語が母国語のひとつだし、『ele-king』で日本語圏に向けて取り上げるべき人ですよ。最近ではジェットセットでもレヴューを書いてたな。彼女はレズビアンであることを公言していて、昔Twitterには自分のことをテクノ・フェミニストと呼んでいてかっこいいなと思いました。
野田:へー、それも興味深い。
高橋:そういうコミュニティからロレイン・ジェイムスがでてきてるっていうのは、ひとつありますね。いわゆる団体というよりも、友だちって感じですけど。
野田:ロンドンって再開発して物価が上がってボヘミアン的なアーティストが住めないって聞くから、もう新しいものは生まれないって思ってた。そういうわけじゃないんだね。
高橋:そんなわけでもないですよ。たしかにブレグジットの影響でボーダーは前ほど自由ではないけど、音楽シーンにインターナショナルな感じはあるかな。TSVIはイタリア人なので。ヨーロッパから人がたくさん集まってる。ベルリンみたいな雰囲気もあります。
123

![【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App 【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_7/2022/3/3/66755df992ff2d2b1e1ab43844ef9f88_0.jpeg)