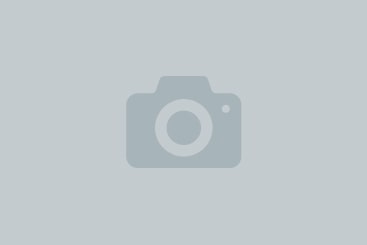東京五輪舞台に世界へ最新技術発信、...
08
09
東京五輪舞台に世界へ最新技術発信、無観客でもポストコロナに活路 - Bloomberg
最新テクノロジーを世界に披露する絶好の舞台だった東京五輪大会は無観客開催となり、PRの機会は大半が失われた。革新技術を提供した企業は開発に至る経験やノウハウなどを東京大会のレガシーとして生かし、ポストコロナ時代につなげようとしている。
江の島の海に浮かぶ長さ55メートルの巨大スクリーン。沖合で行われるセーリング競技を3000人超が観戦するはずだった。4Kカメラやドローンの映像データを5G通信で集約してリアルタイムに合成する技術は、風を捉える帆の動きや波しぶきまで映し出す。望遠鏡を使う従来の競技会場での観戦スタイルを大きく変えるものだ。
開幕2週間前に無観客が決定し、巨大スクリーンは競技の模様や家族の声援を選手や大会関係者に伝えるモニターの役割を担うことになった。NTTの研究所で開発を主導した木下真吾氏は、バドミントン競技を約30キロ離れた会場で立体的なホログラフィック映像として再生し、目の前でゲームを見ているような臨場感を味わえるシステムも開発したが、一般参加者を招くライブビューイングは中止となった。
大会からの発信はできなかったが、木下氏は五輪に関わったことで普段の企業開発では発想できなかった技術が生まれたと感じている。巨大スクリーンに観客を映して手前にホログラフィックでライブパフォーマンスを再生すれば、有名アーティストのライブが世界中で同時に楽しめると、ポストコロナの新技術活用に思いを巡らす。
東京五輪・パラリンピック組織委員会は「史上最もイノベーティブな大会」の実現に向けて、世界最高水準のテクノロジーを競技会場の整備や大会運営に活用することをコンセプトの一つに掲げた。2017年にイノベーション推進室を立ち上げ、NTT、パナソニック、インテル、アリババグループ、トヨタ自動車などと協力し、「新しいスポーツの見せ方」などに関わる企画を進めてきた。
イノベーション推進室A&V企画担当部長の小柴恵一氏は、オリンピックを機に各企業の知識や技術を集積するプロセスは貴重だったと振り返り、今回の経験をレガシーにしたいと語る。

7月23日の開会式で話題を呼んだのが、国立競技場の夜空に市松模様の大会エンブレムや青い地球を立体的に描いた高輝度発光ダイオード(LED)搭載ドローン群によるショーだ。開発したインテルは開会式のコンセプトが1年延期で変わる中、組織委と綿密なコミュニケーションを取ってプログラムを練り上げた。
五輪プログラムオフィス本部長のリック・エチェバリア氏は、あらゆる周波数の電磁波が飛び交う都心の狭い空間で1824台ものドローン飛行を成功させるのは至難の業だったと明かす。東京では4回のリハーサルを行ったという。
開会式では、パナソニックの最新プロジェクターが、赤いひもとダンサーが絡み合うパフォーマンスを演出した。開発責任者の山本祐介氏は、鮮明な赤色を映し出すために限られた時間で試行錯誤を重ねた。
五輪を旗印に組織横断的な開発を進めた結果、通常より半年短い1年で製品化が実現した。5月に国立競技場に設備を設置して試験を繰り返したことで、雨風にさらされた場合の影響も検証でき、今後のソリューションビジネスにもつながると語る。
無観客五輪で観戦ツールとなるのはテレビや公式動画サイト。1998年のバルセロナ大会から放送システムを支えてきたパナソニックで放送システム責任者を務める大西歩太氏は、「最もチャレンジングで不安だらけだった」と話す。
新型コロナによる入国制限で機材テストすらままならない中、20年に1度の技術革新と位置付ける本格4K放送に取り組んだ。東京五輪の放送時間は、前回のリオデジャネイロ大会より30%増の約9500時間に及ぶ。ディテールにこだわった映像技術で配信ができたことで、世界の人々が平等にスポーツを楽しむ機会の創出に貢献できたと感じている。
今回の大会でメディア関係者に提供され、意外な人気を呼んでいるのがアリババクラウドの「デジタルピン」。ピン同士をタップするだけで会員制交流サイト(SNS)の連絡先を交換できる。約200の国と地域から参加する放送関係者とプレス関係者合わせて約1万6000人が行き来するメディアセンターでは、ピンを付けた人同士が声を掛け合う姿が見られた。
アリババクラウドは、大会スタッフの熱中症リスクをリアルタイムに把握するシステムも提供している。耳に装着したデバイスが体温や心拍数を計測し、会場ごとに気温や湿度、日射量などを図るデータと合わせて熱中症警戒アラートを鳴らし、水分補給などの通知メッセージが配信される。


![【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App 【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_7/2022/3/3/66755df992ff2d2b1e1ab43844ef9f88_0.jpeg)