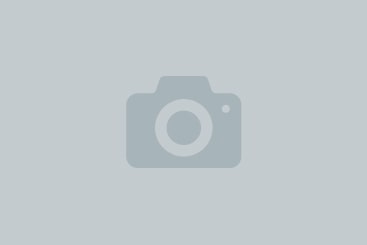ミレニアル世代の住体験にコンサルコ...
11
07
ミレニアル世代の住体験にコンサルコマース、注目あつまる「世界の250社」まとめ(4/4) | BRIDGE(ブリッジ)テクノロジー&スタートアップ情報
1編ではエンタープライズ、フード領域、2編ではフィンテック、教育、ギグ経済領域を見てきました。3編ではヘルスケア、メディア、トラベル市場で起きている変化を紹介しました。最終編となる本記事では、不動産、小売、モビリティに触れて、連載を締めくくりたいと思います。
一軒家を購入するには多額の頭金が必要となります。そこで登場したのがイギリス発の共同オーナーシップ不動産購入サービス低所得者向け住宅ローンサービス「Divvy」。同社はクレジットスコアが著しく低い550以下の顧客を対象に、物件購入をサポート。約5万ドルから20万ドルの価格帯の物件を取り扱います。
顧客が購入希望物件の2%以上の支払いを済ませ、残りの最大98%をDivvy Homes側が負担。同社負担額は顧客が毎月返済し、最大3年をかけて物件所有権の10%に当たるまで支払いが続きます。支払い終了時には、顧客のクレジットスコアが580にまで上昇している目算で、それを超えると金融機関などからローンを組むことができます。ローン借り入れが決まれば、借り入れ額がそのままDivvyへ支払われる仕組みです。住宅購入から住宅ローン借り入れまでの橋渡しをしているのがDivvyというわけです。
似たようなコンセプトとして、イギリス発の共同オーナーシップ不動産購入サービス「Unmortgage」が挙げられます。顧客は購入金額の最低5%を支払うだけでUnmortgageと共同して住宅を購入することができます。居住者は毎月一定の賃貸料を支払い続けることで住み続けられます。賃貸に加え、Unmortgage側が負担した最大95%の住宅購入額を毎年一定額ずつ買い戻していきます。顧客の所有オーナーシップ率が100%になり次第、物件が自分のものなります。
仮に何年か住み続けた後に転居を決めた場合、所有オーナーシップ率を買い戻してもらえるのでキャッシュバックが発生します。月額賃料を支払いながら住み続けられ、気に入ったらオーナーシップを買っていく、「所有」と「共有」を橋渡しするビジネスモデルです。Unmortgageの場合はDivvyとは違い、住宅体験をサブスク化させ、かつ一軒家購入までの検討期間を顧客に持たせています。類似事例として全米トップクラスに住宅価格が高騰するサンフランシスコでの住宅購入に特化した「ZeroDown」がいます。
Divvy、Unmortgage、ZeroDownは高級商材を購入するためのブリッジとなるサービスで急成長しています。ここで注目すべき点は、なんでもレンタル/共有する時代になっていると思われがちですが、未だに「所有ニーズ」が多いに存在する点です。おそらく今後も一定の所有ニーズ層が存在し続けるはずです。こうした顧客に対し、所有のハードルを下げるような価値提供のできる、本項で紹介したようなスタートアップが活躍できるでしょう。
民泊市場では「高級ブランド志向」と「ソーシャルライフ」がキーワードになっていると感じた1年でした。まずは高級ブランド志向からお話しします。
Airbnbを筆頭に大手サービスに市場はほぼ取られてしまい、各社が次に攻めたのがアパート部屋の賃貸や自社運営の民泊拠点の貸し出しです。たとえば、Airbnbが巨額投資をしている「Lyric」が挙げられます。同社はアメニティが完備され、アプリを通じた24時間カスタマー対応付きのアパート民泊を運営。また、「WhyHotel」は空き部屋の多い新築マンションを高級アパート民泊サービスとして貸し出しています。「Sonder」は自社で物件を所有し、ネットワーク全ての部屋を自社ブランドに統一して貸し出しています。
それぞれAirbnbより比較的割高な価格帯でサービスを提供。その裏には、「高いキュレーション」が求められる市場需要が伺い知れます。部屋の管理からインテリアデザインまで、各社とも高い質を提供しています。キュレーションが求められる理由として、ネットワークビジネスでしばしば発生する、質の悪いサービス提供者に嫌気が差している一定層が存在している点が挙げられます。
この点、AirbnbはLyricに投資することで、民泊市場の低価格層から高級層まで、ほぼ全ての顧客の需要に応えようとする戦略を持っていると想像できます。ちなみに、ホテルと同等の質を求めるビジネスマンからの需要は高く、「Zeus」や「2nd Address」がビジネス層をターゲットにしています。
中長期の住居を提供するコリビングサービスでは、同世代の若者が集まる「ソーシャル要素」が鍵となっています。ブランディングの一環として、旅行者や居住者との交流は欠かせない要素となっています。しかし、コリビングスタートアップの多くがSonder同様に自社ブランドとして場所を提供しているため、Airbnbのようなネットワークモデルではなく、住宅やホテルを又貸しするWeWorkに似たビジネスモデルを採用。ただ、このモデルでは巨額のコストがのしかかるでしょう。たとえば、「Life House」のようなホテル事業者が事業者が挙げられます。
今回リスティングした企業の大半が、WeWorkの上場撤回事件が発生するまでに資金調達を完了しています。WeWorkのようにユニットエコノミクスが成立していなくとも、ミレニアル世代が求めるソーシャルやコラボレーション価値を前面に押し出すことで成長を続けられてきた、言わば“バブル勢”と捉えられます。
今後は“WeWork後”の正念場を試される立場になることは必至でしょう。又貸しモデルで調達を続けてきた民泊およびコリビング勢は、2020年以降、投資家からの厳しいファイナンスチェックが入ることは容易に想像がつきます。
「thredUp」の2019年レポートによると、米国中古アパレル市場は2023年に510億ドルにまで成長すると予測されています。これは2018年の240億ドルの2倍強の規模です。また、アパレル市場と比べて中古市場は21倍も早い速度で成長しているとのこと。なかでも女性層の成長は強く、2018年に5,600万人が中古アパレル商品を購入した経験があると分析。前年度比4,400万人から大きく前進しています。市場の16%を占めるZ世代購買者は、3人に1人が今後中古品を購入したいと希望していることから、各社とも次のターゲット市場として狙いを定めています。
今回リスト入りしている中でも、「Bump」や「Depop」などのストリートファッション商品を展開するサービスはZ世代を取り込んでいる模様です。「thredUp」「TheRealReal」「Poshmark」はミレニアル世代には人気である一方、Z世代の取り込みはまだ不十分な印象です。この点、Z世代から爆発的な人気を誇る、次のアパレルリセール市場で急成長を遂げられる可能性がスタートアップに残っています。既存サービスの体験を次世代向けにアップデートするスタートアップに商機が訪れるでしょう。
レポートの中で興味深い動向として指摘されているのが、コンマリメソッドの普及。部屋を掃除して、本当に大切なものだけを残し大切に使う“Konmari”の考えがリセール市場にも広がりつつあります。コンマリした人は不用品を2次流通を利用するため市場を活性化させます。実際、Netflixでコンマリ番組が配信された直後は、要らない洋服を詰めてそのままthredUpに出品できる「Clean Out Kit」の提供数が80%上昇したとのこと。Konmariに代表される新しいコンセプトが市場を底上げしている動きは覚えておくべきかもしれません。デジタルコンテンツとリセール市場に強い導線が出来ていることがClean Out Kitの実績からわかるため、メディアの視点からもリセール市場参入を検討できそうです。
リセール市場向けプライベードブランド化の動きもあります。「Rent The Runway」は自社貸し出しサービス専用のブランドを作っており、thredUpもリセール向けの洋服ラインを構築。新しいものではなく、長くいろんな人の手に渡ることを想定して作られたファッションブランドが市場で出来つつある点が見逃せません。多くのブランドが生まれていますが、プラットフォームと連携して洋服を卸す、リセール特化ブランドが誕生してもおかしくないでしょう。

単独アプリやWebサービスが欧米ライブコマース市場を制するのは厳しい印象です。大きな理由としてGAFAが本格的に動き始めたことが挙げられます。Facebookは、12月20日、ローカルコミュニティ内で中古品を売買できるフリマ機能「Marketplace」にライブコマースを実装するため、動画ショッピング機能を開発するスタートアップ「Packagd」を買収したと報じられました。Facebookは2018年、タイでライブコマース機能を試験投入していることから、米国市場で同機能を再現するとされています。
ライブコマースは中国市場で爆発的に普及しています。独身の日セールでは、AlibabaやTencent傘下のEコマースサービスで28億ドル規模のライブコマース経由の購買が行われています。一方、米国市場では中国ほどの売上を上げている印象はありません。たとえば、今では米国世帯の半数がPrime会員に加入しているとはいえ、Amazon Prime Dayにライブコマースが売上を伸ばしているといった話は聞きません。
そこで登場するのがFacebook。従来、Marketplaceはローカル特化のフリマとして成立していましたが、もしライブコマース機能が実装されれば、国が離れていたとしても個人間売買を促進できます。つまり、これまでローカルだった場所が、急にグローバルなネットワークへと成長するとっかかりを得るのです。ちなみにInstagram Liveが自社プロダクト内で競合になってしまうかと思われますが、Facebook MarketplaceとInstagramは利用シーンが大きく違うため、ユーザーの共食いをすることはないでしょう。
しかしFacebookは大きな商機を逃しています。というのも、最もライブコマースがホットな中国市場に参入しようとしても出来ないのです。このGAFAの参入障壁を狙っているのが欧米のスタートアップたち。たとえば米中をライブコマースで繋ぐ「ShopShops」や、インフルエンサーが店舗からライブ動画配信する「roctona」が挙げられます。彼らは中国市場向けに越境ビジネスを仕掛け、ライブ配信者ネットワークを構築しています。
GAFA勢の穴を埋めるように、スタートアップは成長を遂げています。日本でも「Live Shop!」などが人気ですが、仮に中国市場向けにアパレル・医薬品商品を販売するライブコマースアプリへと方向性を変えれば成長が狙えるかもしれません。ここで覚えておくべきことは、GAFAが取りこぼした大きな商機が中国顧客を前提とした越境市場に潜んでいる点です。この点を見逃さず、配信者ネットワークを世界規模で展開できた企業は、ライブコマース市場で勝ち抜けられるはずと感じます。
専門家の意見を聞きながら、最適な商品を購入するパーソナライズ体験は見逃せない動きでしょう。購買活動において、コンサルタントを雇う体験が人気です。このコンセプトは2編で紹介したパッションエコノミーと強く結び付いています。「Curated」は専門知識のある人が、お客さんと一緒に商品を選ぶ体験を提供。これは個々の強みを活かしてサービス化させるトレンドを掴んで生まれたサービスと言えます。小売市場swhパーソナライズ体験の重要性が叫ばれて久しいですが、コンサル・コマースはその解の1つを指し示しています。
米国スタートアップ界隈では店舗業態を販売から不動産へシフトさせる動きが始まっています。代表的な企業に「Bulletin」が挙げられます。月額2,000〜3,000ドルで店舗一画を各ブランドの販売商品の展示スペースとして割り当てる不動産事業を展開。EC事業者が手軽に一等地店舗に商品を並べる機会提供を行っています。店舗側は場所を貸し出すだけのモデルであるため、あとは簡単な商品在庫スペースだけあれば十分です。
売り場だけ確保できれば良いため、従来型の店舗と比べて1坪当たりの売上上昇に注力できます。さらに月額サブスクリプションモデルのため店舗側は一定売上が担保されます。販売売上に左右されずに一定の売上予測が可能になるのです。出店ブランド側も多額の出店費用リスクを負う必要がなくなるWin-Winの関係構築をしました。
最近では「Neighborhood Goods」や「Showfields」のように、デパート規模の大きなハコでBulletinのようなシェアリング店舗事業を展開する事例が目立ちます。また、お客さん同士の交流や、イベントにも注力した新しい娯楽施設としての側面を持たせる動きもあります。こうした動向から、ポスト2019年の店舗はシェアリング不動産事業をベースに、顧客体験を最大化させるエンタメ化が加速するように思えます。先述したデパートスタートアップが提供する体験コンテンツが、どの程度客単価を引き上げるかは未だ実験段階であるため、今後何かしらのソリューションが登場してくることが望まれます。
物流市場では対Amazonをサポートするサービスが登場しています。Amazon Primeの登場以来、即日配達サービスが当たり前になってしまいました。しかし、既存小売店がすぐに即日対応できる物流網を準備できるはずがありません。そこで登場したのが「Darkstore」。都市部に特化したフルフィルメントサービスを展開しています。利用企業は当日配達サービスを手軽に展開できるようになります。物流面でAmazonに対抗する武器を、高速で販売店が実装できるサービスとして実績を伸ばしています。
また、Amazonでは返品できるのが当たり前。欧米では日本と比べて返品率が高いため、どの小売店も返品サービスを付けておかなければAmazonに客が取られてしまいます。ただ、当日配達同様に、サービス実装には多大のコストが必要。この課題を解決するのが「Happy Returns」です。提携ECブランド商品であれば、顧客は最寄りのショッピングモールに開設してあるHappy Returnsのブースで返品作業を行えるサービスを提供します。顧客は箱詰めして送り返す手間暇を省け、返品対象品を手渡しするだけで即金でお金を得られるメリットがあります。
同社は各ブランドへの返品数が一定数以上集まってから返送・配達を行います。返品物流を小分けではなくまとめ配達の物流手法へと変えたのです。1品ずつ返品するのでは、EC事業側の管理コストがかかり過ぎますし、物流業者の仕事が増えてしまいます。この課題を解決したのがHappy Returnsなわけです。このようにAmazonが得意とするサービス領域を自社で作り出し、パートナー企業へ提供するアドオン事業が物流市場で成長しているのが印象的です。日本では運送業者の過剰労働が社会問題になったことから、本項で紹介したスタートアップを模倣した事業に支持が集まるかもしれません。
洋服サブスクスタートアップ「Le Tote」が老舗デパート「Lord & Taylor」を買収したニュースは衝撃でした。この買収劇から予想できるのは個客管理の可能性です。たとえばデパート入り口で、Le Toteのユーザーアカウント認証を行うタブレット導線を用意した場合、オンラインアカウント情報と店舗内で購入した商品データとの連携に成功します。データ連携の最大のメリットは、Le Toteのオンライン店舗とLord & Taylor内の購買データを統合させることで、オンラインとオフラインのどちらのチャネルから顧客が流入しても、最適な商品提案が可能となる「オムニチャネル戦略」を採用できる点にあります。
Amazonが成功している点もまさにここ。無人店舗「Amazon Go」の来客は入り口でアカウント認証が必要です。これは店舗内購買データをAmazon Marketplaceでも活かして、最適な商品レコメンドをするための導線を確保するためのものです。つまり実店舗顧客はオンライン・マーケットプレイスに来てもAmazonにターゲティングされ、高い精度のパーソナライズ商品提案される対象になるのです。
Le ToteはもともとEコマース企業。デパート体験をオムニチャネル戦略を採れるように最適化させることは想像に難くありません。改めてリストを見てみると、2019年は大型倒産や買収が相次ぎましたが、オムニチャネル戦略を匂わせるディールはAmazonの生鮮食品ブランド店舗のニュースのみ。たとえば、Old Navyが単に店舗を増やしたとしても、提供価値や戦略上の甘さで、Le Toteのようなスタートアップに買収される対象になってしまうかもしれません。また、Forever 21に代表される大手アパレル企業がドミノ倒しに破産申請していく可能性も否めません。顧客体験を最大化させる新業態や戦略採用が急務となりそうです。こうした流れは、ゆくゆく日本の小売市場でも顕著になってくるはずでしょう。
空飛ぶタクシーはいよいよ実用化に向けて本格始動。欧州ドイツや米国カリフォルニア州を中心にスタートアップが活躍している印象です。上記のリストには入っていませんが、ドイツ拠点の電動空飛ぶタクシー企業「Lilium」も数億ドル単位で資金調達を模索しています。市場の動きを見ていると、3-5年以内に高価格ながら商用化されそうです。
注目なのは空飛ぶタクシー時代の“プロバイダー”の市場ポジションを狙う企業が出てきている点です。具体的にはタクシーが離着陸するための「ミニ空港」を作り上げる企業たちが挙げられます。「Skyports」のようにビルの屋上に滑走路を作ったり、都市部の空きスペースに専用小型空港を建てて、次世代の“管制塔”を目指しています。
機体開発と空港整備の両方が進み、いずれ空飛ぶタクシーの輸送は地域間の新たな移動手段として確立されるはずです。ここで真剣に考える必要があるのがディスラプト。空飛ぶタクシーが飛び始めると、中距離移動手段がディスラプトされる可能性を考える必要があります。たとえば高速バス移動手段の優位性が揺らぐかもしれません。また、郵便物輸送などの簡易な物流に変化が訪れるかもしれません。都市部とベッドタウン、もしくは地方間における輸送や物流は大きく前進することが予想されます。
さらに、ロケットの高速生産が始まる動きも見逃せません。機体数が増えれば、打ち上げ需要も自ずと増えてきます。こうした需要に対して、打ち上げ拠点の供給は間に合っていないでしょう。そこで、基地ビジネスやライドシェアに注目が集まるはずです。たとえば北海道などで広大な土地所有権を持つ人が、簡単な打ち上げ基地を作りあげられるサービスや、時間別にスムーズに打ち上げができるオンデマンド型の打ち上げ事業が生まれてくるはずです。実際、Sequioa Capitalが投資をした「Vector」が打ち上げ基地ビジネスに着手していました。また、「Loft Orbital」が小型衛星のライドシェア事業に取り組んでいます。こうした次世代の宇宙ビジネスに注目が集まるでしょう。
さて、250社のまとめ紹介はここまでです。1編から最後まで読んでくださった方は、最新欧米スタートアップ事情にかなり精通できるまで事例がインプットされていると思います。その上で、新しい事業構想を考える上で参考になる企業が1社でも見つかれば幸いです。
ただ、1点伝えなければいけないのは、4編を通じて紹介した30のキーワードは全て市場で十分に裏付けをされたもの。日本で起業や新規事業立ち上げをする上では通じるかもしれませんが、世界で戦うアイデアを探す上では、そのまま真似しても勝てません。3-5年は遅れをとってしまっていると言って過言ではないでしょう。
トレンド情報はメディアで消費されやすいものですが、事業の急成長性には欠けてしまいます。そのため、単にキワード情報をインプットするのではなく、全く市場からキーワードを引っ張ってきて掛け合わさせる思考法をおすすめします。新しいアイデアは必ず異業界のコンセプトを移植させ、化学反応を起こすことで誕生することがしばしばあります。この点は『模倣の経営学』に詳しく書かれているため、時間を取って読まれることをおすすめます。
また、第1編の冒頭でもお伝えしましたが、「Accessibility」が鍵になっています。各企業が既存概念をどのように民主化させ、私たちの共感を得られる体験にまで最適化させているかを考えれば、いろいろと発見があるはずです。
改めて、最後まで読んでいただいてありがとうございました。本連載がみなさんにとって実りある“ポスト2019年”を迎える一助になれたらありがたい限りです。
BRIDGEでは会員制度「BRIDGE Members」を運営しています。会員向けコミュニティ「BRIDGE Tokyo」ではテックニュースやトレンド情報のまとめ、Discord、イベントなどを通じて、スタートアップと読者のみなさんが繋がる場所を提供いたします。登録は無料です。無料メンバー登録


![【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App 【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_7/2022/3/3/66755df992ff2d2b1e1ab43844ef9f88_0.jpeg)