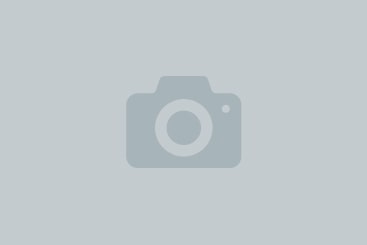英国船が江戸時代に運んできた「スト...
09
03
英国船が江戸時代に運んできた「ストーブ」は、ニッポンで大いなる進化を遂げた
CBCテレビ:画像『写真AC』より「ストーブ」

暖を取るための手段として、古来、西洋には暖炉、日本には囲炉裏に火鉢があった。そんな中、江戸時代にイギリスからやって来た「ストーブ」は、次々と燃料を替えながら、日本で独自の進化の道を歩んでいく。暖房器具である「ストーブ」を広めたのは、米国の物理学者であり政治家でもあったベンジャミン・フランクリンだと言われている。凧を使って、雷が電気であると実験証明したことでも知られるフランクリン。暖炉の効率を良くするため、何か暖かい空気を作って発散させる方法はないかと考えた。そこで、鉄製の箱の中に火を点けた薪を“閉じ込める”ことで熱を発生させて、鉄を通して周囲に暖かい空気を送る「薪ストーブ」を発明した。この薪ストーブは米国の家庭に一気に広がっていった。
CBCテレビ:画像『写真AC』より「薪ストーブ」
江戸時代末期の1856年(安政3年)、まだ蝦夷地と呼ばれていた北海道、その箱館の港に(現在の函館市)、一隻の英国船が寄港した。3年前に黒船を共に来日したペリー提督の要望で箱館も外国に対して港を開いていた。北の海の寒さを凌ぐため、船には薪を使ったストーブが備えられていた。部屋を暖める“ストーブなるもの”の存在を聞きつけた箱館奉行は、早速、奉行所から見分のために配下を派遣した。「何とか手に入れたい」と、その暖房器具を絵に描かせて、早速、同じものを作るように、鋳物屋に注文した。出来上がってきたのは、石の台の上に、直径50センチ、高さ40センチの銅でできた丸い筒、銅の厚さは0.5センチだった。丸い筒の一部には、土管をつなぎ合わせた煙突が付いていた。これが、日本で作られた最初の「ストーブ」、薪ストーブの第1号となった。銅製の筒の中で薪を燃やし、その熱が銅を通して周囲に暖かい空気を送った。この薪ストーブは、北方警備に派遣された役人たちの防寒対策に役立てられた。明治時代に入って、蝦夷地は「北海道」と名前を替えて、多くの開拓民がやって来たが、凍てつくような厳しい寒さの中で、薪ストーブは大いに重宝された。薪から始まった、日本での「ストーブ」は時代ごとに燃料を替えながら成長していった。石炭を使ったストーブが登場したが、炭をつぎ足す時に、中の粉塵が部屋の中に舞ってしまうという欠点もあった。次にお目見えしたのが石油を燃料とするストーブだった。1955年(昭和30年)に完成した日本で最初の「加圧式石油ストーブ」は国内に普及していく。「日本の暖房を変えた」とまで高い評価を受け、その後「石油ファンヒーター」へと成長していった。
最終更新:CBCテレビ

![【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App 【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_7/2022/3/3/66755df992ff2d2b1e1ab43844ef9f88_0.jpeg)