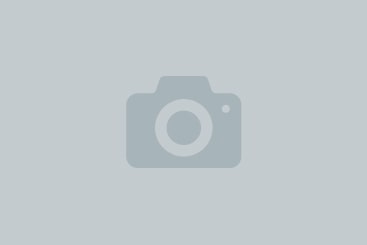濱口竜介の理知的な語り、独自の映画...
04
04
濱口竜介の理知的な語り、独自の映画論に唸る。『ドライブ・マイ・カー』における“間”の解釈とは?
配信
2コメント2件『ドライブ・マイ・カー』濱口監督がLAのオンラインイベントに登壇

全米映画批評家協会賞作品賞、第79回ゴールデングローブ賞非英語映画賞などアメリカでの受賞が続いている『ドライブ・マイ・カー』の濱口竜介監督が、米ロサンゼルスのジャパン・ハウス・ロサンゼルスが主催したオンラインイベントに登壇した。【写真を見る】国内外で数々の賞を受賞、米国アカデミー賞のノミネートも期待される『ドライブ・マイ・カー』第94回アカデミー賞の各賞ノミネーション発表は、イベントから1週間後の現地時間2月8日。いまの心境を「アメリカで『ドライブ・マイ・カー』が受け入れられる状況は想像していなかったので、とても驚いています。アカデミー賞についても聞かれますが、こればかりは成り行きで、どうなるかはわかりません。いまの時点で十分評価をいただいていると感じているし、このことによって観客が映画館へ向かい、この映画を観てくれるというのが一番嬉しいことです。もし“なにか”が起きたらそれはご褒美だと思っています」と率直な感想を述べた。ロサンゼルスおよびハリウッドの印象については、「自分が最も影響を受けてきたジョン・カサヴェテスは、ハリウッドで俳優をやりながらインディペンデント映画を作る、世界でもあまりいない存在でした。ハリウッド映画自体も大好きですし、彼のインディペンデントな映画の作り方にずっと勇気づけられてきています。この間、生まれて初めてロサンゼルスに降り立ち『これがカサヴェテスたちが仕事をしていた街か』と思うと非常に興奮するところがありました。ぜひまた訪れたいと思っています」と、抱負を語った。イベントのテーマは「日本映画における間(スペース)」。建築学を専門とするカリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) の阿部仁史教授と、ワシントン大学のケン・タダシ・オオシマ教授による『ドライブ・マイ・カー』における「間」の解釈のもと、濱口監督は「“間”に関してあまり概念的に考えたことはありませんでしたが、撮影現場では『もうちょっと間をとってください』など、よく使う言葉です」と話を始めた。村上春樹の原作小説と映画の「間(あいだ)」について「映画とはそもそもフィクションと現実の間にあるもの」とする。「カメラを使って映画を作る最小の単位に“ショット”があり、空間と時間を区切るものです。まず、フレーム(画角)によって空間を区切らなくてはいけない。そしてカメラの回し始めと終わりにより、時間を区切らなくてはいけない。どこからどこまでを区切るかが監督の仕事だと言ってもよいと思います。この作業において、現実とフィクションの間(はざま)がすでに発生します。というのは、カメラというのは人間の知覚能力より遥かに優れた光学的記録能力を持っているので、現実そのままの知覚的記録がなされます。一方で、これは現実のすべてを記録したものではなく、空間的・時間的断片としてしか捉えることができません。これは現実の映像ではなく、フレームの外側やカメラを回し始める前になにが起きているかわからないので、そこには常にフィクションの可能性があります。ショットを撮るという映画の最小単位の中に、すでにフィクションと現実が存在しています。この断片と断片を組み合わせ、現実とはまったく違うもう一つの現実みたいなものを作り上げていくのが劇映画、フィクションになります」。劇中、家福(西島秀俊)とみさき(三浦透子)を乗せた赤い車は、映画の前半では安芸灘大橋を渡り、後半ではいくつかのトンネルを抜けていく。その「間」についての考察に対し、濱口監督はこう答えた。「橋は、レイヤーを一望できる場所です。一つのレイヤーがあり、もう一つのレイヤーに向かい、その先にはまたレイヤーがある。トンネルは、それが目隠しをされている状態で、どこを走っているのかわからないぶん、抽象度が高い空間になります。後半に行くにつれてトンネルの描写が増えていくのは、この映画の抽象度が上がっていくことと比例しています。空間も時間も凝縮されたものになり、昼のショットからトンネルを抜けると夜になり、晴れている空間からトンネルを抜けると雨が降っているなど、トンネルを抜けるとすでに変わってしまっているところを編集で選びました。トンネルを潜り抜けることで、キャラクターも変わっていき、それが観客にも届く変化になると思っています」。小説と映画の“間”、アダプテーションについて「文学作品が優れていればいるほど、単に文章を映像に置き換えるだけでは、文章が作り出している感動を味わうことはできません。映画は映画のやり方で、現実とフィクションの間を捉えてしまうカメラの能力を使いながら、小説をどう映画にする方法があるのかと考えていく必要があります」と語る。その際に重要になるのがテキスト(=脚本)だ。「(小説と映画の)中間的な存在として、演劇が存在しているのではないかと思います。演劇は書かれたテキスト、口語ではないものを口にする特殊な行為です。一方それが正当化される場で、観客は不思議には思いません。村上春樹さんが書かれたテキストがベースにありますが、チェーホフは本当に強い力を持っていると思いました。テキストを役者の体に保存し、それが相手との相互作用によって感情を引き出すものですが、チェーホフのテキストを使ったときに出てくる感情の量は半端ない(笑)。チェーホフのテキストには、現実とフィクションの境界をなくしてしまうような、人々の体に直接訴えかけるような力を持っていると思いました」。およそ1時間程度行われたオンラインのイベントだが、異分野の専門家との対話から、濱口竜介監督が捉える映画の定義や、彼を魅了する演技の神秘性などについての考察が語られた。映画についてのティーチインやシンポジウムでは、映像美や役者の身体性についての感覚的な議論は多く見られるが、濱口監督の言説は常に理論的。アメリカの映画業界で活躍する監督・プロデューサーには、映画学校でこうした映画理論を徹底的に叩き込まれた人が多い。濱口監督は、既存の理論に独自の解釈を重ね合わせ映画を作り、それを的確に言語化しているところが、アメリカおよびハリウッドでの評価につながっているのではないだろうか。このイベントのアーカイブ映像は、後日ジャパン・ハウスの公式サイトにもアップされるそうだ。文/平井伊都子
最終更新:MOVIE WALKER PRESS

![【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App 【個人開発ゲームを斬る】アプリ史上トップクラス! 美しすぎる水のパズル『a[Q]ua』 | スマホゲーム情報ならファミ通App](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_7/2022/3/3/66755df992ff2d2b1e1ab43844ef9f88_0.jpeg)